【徹底比較】防災用エアーマット選びで後悔しない!タイプ別おすすめと選び方ガイド
※この記事にはアフィリエイト広告が含まれています。

「もしもの時」に備える防災用品。
食料や水、懐中電灯は準備していても、意外と見落としがちなのが「睡眠環境」ではないでしょうか。 災害時、避難所での生活は想像以上に過酷です。
硬い床での睡眠は、身体への負担はもちろん、精神的なストレスも大きく、体調を崩す原因にもなりかねません。 そんな時、エアーマットがあれば、まるで自宅のベッドで寝ているかのような快適さを手に入れることができます。
しかし、いざ選ぼうとすると、種類が多すぎて「どれを選べばいいの?」と迷ってしまう方も多いはずです。 「本当に必要な機能は?」「持ち運びやすさは?」「家族みんなで使える?」
そんなあなたの悩みに寄り添い、最適なエアーマット選びをサポートします。
この記事を読めば、あなたと家族にぴったりの防災用エアーマットがきっと見つかります。
なぜ防災用エアーマット選びはこんなに難しいのか?

防災用エアーマットと一口に言っても、その種類は多岐にわたります。
自動で膨らむタイプ、手動で空気を入れるタイプ、連結できるタイプなど、機能も価格帯も様々です。 インターネットで検索しても、情報が多すぎて何が自分にとって最適なのか判断しにくいと感じることはありませんか?
「コンパクトさを重視すべきか、寝心地を優先すべきか」
「家族の人数分揃えるべきか、それとも共用できるタイプが良いのか」
といった疑問が次々と湧いてくるかもしれません。 また、普段使いするものではないため、実際に試す機会も少なく、購入後に「こんなはずじゃなかった」と後悔するケースも少なくありません。
特に、災害時に本当に役立つかどうかは、実際に使ってみないと分からない部分も多いですよね。 このような選択肢の多さと、情報収集の難しさが、エアーマット選びを複雑にしている大きな要因です。
しかし、ご安心ください。
この記事では、主要なエアーマットのタイプを分かりやすく解説し、あなたの状況に合わせた選び方のヒントを提供します。
防災用エアーマットの「自動膨張式」の魅力
特徴とメリット
自動膨張式エアーマットは、バルブを開けるだけで自動的に空気を吸い込み膨らむのが最大の特徴です。
手動で空気を入れる手間が省けるため、災害時のような緊急時でも素早く設置できるという大きなメリットがあります。
内部にウレタンフォームが内蔵されており、これが空気を取り込むことで膨らむ仕組みです。 そのため、万が一穴が開いて空気が抜けてしまっても、ウレタンフォームがクッション材として機能し、完全にぺたんこになることを防いでくれるという安心感もあります。
厚みがある製品が多く、地面からの冷気や硬さをしっかりと遮断してくれるため、快適な寝心地を提供してくれます。
特に、冷え込みが厳しい季節や、硬い体育館の床で寝る際には、その恩恵を強く感じられるでしょう。
想定される利用シーン
このタイプは、特に迅速な準備が求められる避難所生活や、キャンプなどのアウトドアシーンで活躍します。
小さなお子さんがいる家庭や、高齢者の方など、体力に自信がない方でも簡単に設置できるため、家族全員が安心して使える防災用品としておすすめです。
また、車中泊での利用にも適しており、長時間の移動で疲れた体を休めるのに役立ちます。
自動膨張式エアーマットのメリット・デメリット
- メリット:
- バルブを開けるだけで簡単に設置できるため、手間がかかりません。
- 内部のウレタンフォームにより、高いクッション性と保温性があります。
- 地面からの冷気や硬さをしっかり遮断し、快適な寝心地を提供します。
- 万が一の破損時も、ウレタンフォームがクッション材として機能します。
- デメリット:
- 収納サイズが他のタイプに比べてやや大きめになる傾向があります。
- 完全に膨らむまでに時間がかかる場合があります。
- 価格が比較的高価な製品が多いです。
- ウレタンフォームの劣化により、膨張力が低下する可能性があります。
防災用エアーマットの「手動ポンプ・口吹き式」の魅力(詳細に解説)
特徴とメリット
手動ポンプ式や口吹き式のエアーマットは、その名の通り、付属のポンプや口で空気を吹き込んで膨らませるタイプです。
このタイプ最大の魅力は、その圧倒的なコンパクトさと軽量性にあります。
収納時はペットボトルほどのサイズになる製品も多く、防災リュックの限られたスペースにも無理なく収納できるのが大きな利点です。 また、構造がシンプルなため、比較的安価で購入できる点も魅力の一つです。
複数の人数分を揃えたい場合や、予算を抑えたい場合に適しています。
最近では、足踏みポンプ内蔵型など、より手軽に空気を入れられる工夫がされた製品も増えており、以前よりも使い勝手が向上しています。
想定される利用シーン
このタイプは、持ち運びやすさを最優先したい方や、限られた収納スペースしかない場合に最適です。
例えば、マンションの高層階に住んでいて、避難時に荷物を最小限に抑えたい方や、車を持たず徒歩での避難を想定している方には特に向いています。
また、ソロキャンプや登山など、軽量化が求められるアウトドア活動にも非常に適しています。
災害時だけでなく、普段使いとしても活用できる汎用性の高さも魅力です。
手動ポンプ・口吹き式エアーマットのメリット・デメリット
- メリット:
- 非常にコンパクトに収納でき、軽量で持ち運びやすいです。
- 比較的安価で購入できるため、複数用意しやすいです。
- 構造がシンプルで、故障のリスクが低い傾向があります。
- 足踏みポンプ内蔵型など、手軽に膨らませる工夫がされた製品もあります。
- デメリット:
- 空気を入れるのに手間と時間がかかります。
- ポンプや口で膨らませるため、体力が必要になる場合があります。
- 自動膨張式に比べて、寝心地が劣ると感じる人もいるかもしれません。
- 穴が開くと空気が完全に抜けてしまう可能性があります。
防災用エアーマットの「連結・多人数用」の魅力
特徴とメリット
連結・多人数用エアーマットは、複数のマットを連結させて広い寝床を確保できるタイプや、最初から複数人での使用を想定して作られた大型のマットを指します。
このタイプの最大のメリットは、家族やグループで避難する際に、一体感のある快適な睡眠スペースを確保できる点です。
個別のマットがバラバラになる心配がなく、隙間風も入りにくいため、より暖かく過ごせるという利点もあります。 また、連結することで安定感が増し、寝返りを打ってもマットがずれることが少なく、質の高い睡眠につながります。
特に小さなお子さんがいる家庭では、親と子が隣り合って寝られることで、安心感が得られるだけでなく、夜間の見守りも容易になります。
製品によっては、枕が一体型になっていたり、表面素材が肌触りの良いものになっていたりと、快適性を追求した工夫が凝らされているものも多いです。
想定される利用シーン
このタイプは、家族単位での避難を想定しているご家庭や、グループで行動することが多い場合に特に適しています。
避難所でのプライバシー確保が難しい状況でも、連結マットを使うことで、ある程度のパーソナルスペースを作り出すことができます。
また、キャンプやグランピングなど、大人数でのアウトドアレジャーにも最適で、災害時だけでなくレジャーでも活用できる汎用性の高さも魅力です。
車中泊で家族みんなで寝る際にも、広々とした空間を確保できるため、快適な休息が期待できます。
連結・多人数用エアーマットのメリット・デメリット
- メリット:
- 家族やグループで一体感のある広い寝床を確保できます。
- マットがバラバラにならず、安定した寝心地が得られます。
- 隙間風が入りにくく、保温性が高い傾向があります。
- 小さなお子さんがいる家庭では、安心感と見守りのしやすさがあります。
- デメリット:
- 収納サイズが大きくなりがちで、持ち運びや保管にスペースが必要です。
- 個別のマットに比べて重量がある製品が多いです。
- 価格が高価になる傾向があります。
- 連結部分の耐久性や、空気漏れのリスクが考慮すべき点となります。
防災用エアーマット比較表+選び方ガイド+FAQ

ここまで3つの主要なエアーマットのタイプをご紹介しました。
それぞれの特徴を理解した上で、ご自身の状況に合ったものを選ぶことが重要です。
ここでは、各タイプを比較表でまとめ、さらに選び方のポイントとよくある質問にお答えします。
エアーマットタイプ別比較表
| タイプ名 | 特徴 | 価格帯(目安) | 対象者 | 一言ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 自動膨張式 | バルブ開放で自動膨張、ウレタン内蔵で高クッション性。 | 中~高価格帯 | 手軽さ・寝心地重視、体力に自信がない方、家族向け。 | 設置が簡単で、快適な寝心地を求めるならこれ。 |
| 手動ポンプ・口吹き式 | ポンプや口で空気注入、非常にコンパクトで軽量。 | 低~中価格帯 | 携帯性・収納性重視、ソロ、予算を抑えたい方。 | 持ち運びやすさと収納性はピカイチ。 |
| 連結・多人数用 | 複数枚連結可能、または大型で複数人対応。 | 中~高価格帯 | 家族・グループでの避難、一体感を求める方。 | 家族みんなで快適に過ごしたいなら検討してみては。 |
エアーマット選び方ガイド
エアーマットを選ぶ際は、以下のポイントを考慮すると良いでしょう。 1. 誰が使うか(人数と体力) * 一人暮らしならコンパクトな手動式、家族なら連結式や自動膨張式がおすすめです。 * 高齢者や小さなお子さんがいる場合は、設置が簡単な自動膨張式が適しています。 2. 収納スペースと持ち運びやすさ * 自宅の収納スペースや、避難時に持ち運ぶ際の荷物の量を考慮しましょう。 * コンパクトさを最優先するなら手動式、多少かさばっても快適さを求めるなら自動膨張式が良いでしょう。 3. 寝心地の好み * 硬い床からの冷気や硬さをしっかり遮断したいなら、厚みのある自動膨張式が高い満足度を得られるかもしれません。 * 多少の寝心地は妥協しても、携帯性を重視するなら手動式も選択肢に入ります。 4. 予算 * 価格帯はタイプによって異なります。 * 必要な枚数と予算を照らし合わせながら、最適なバランスを見つけましょう。
よくある質問(FAQ)
- Q: エアーマットはどれくらいの厚さがあれば快適ですか?
- A: 一般的に、5cm以上の厚さがあれば地面からの冷気や硬さを十分に遮断し、快適な寝心地が得られるとされています。特に冬場や硬い床での使用を想定するなら、7cm以上の厚さがあるとより安心です。
- Q: エアーマットの耐久性はどれくらいですか?
- A: 製品や使用頻度、保管状況によって異なりますが、適切に保管・使用すれば数年から10年程度は持つものが多いです。定期的に空気を入れて状態を確認することをおすすめします。穴が開いた場合は、補修キットで修理できる製品もあります。
- Q: 避難所以外でも使えますか?
- A: はい、もちろんです。キャンプや車中泊、来客用の簡易ベッドとしても活用できます。多用途に使える製品を選ぶと、無駄なく活用できるでしょう。
- Q: 空気入れが大変そうですが、コツはありますか?
- A: 手動ポンプ式の場合、製品によっては足踏みポンプ内蔵型や、スタッフサックがポンプ代わりになるものもあります。口吹き式の場合は、一度に大量の空気を入れようとせず、少しずつ確実に入れていくのがコツです。自動膨張式はバルブを開けるだけなので、手間はほとんどかかりません。
購入時の注意点や自然な改善・代替策

エアーマットは防災用品として非常に有効ですが、購入時にはいくつか注意しておきたい点があります。
まず、サイズと重さです。
収納時のサイズが防災リュックに収まるか、持ち運びが可能かを確認しましょう。 特に、家族全員分を揃える場合は、総重量がかなりのものになる可能性もあります。
また、耐久性も重要なポイントです。
安価な製品の中には、すぐに穴が開いてしまったり、バルブが破損しやすいものもあります。
購入者のレビューを参考にしたり、信頼できるメーカーの製品を選ぶことが後悔しないための秘訣です。 保管方法にも注意が必要です。
長期間たたんだままにしておくと、ウレタンフォームの劣化や素材の癒着が起こる可能性があります。
定期的に広げて空気を入れ、風通しの良い場所で保管することをおすすめします。
直射日光や高温多湿な場所は避けましょう。 エアーマットが手元にない場合の代替策としては、段ボールや毛布、衣類などを重ねて敷く方法があります。
これらも地面からの冷気や硬さを多少は和らげてくれますが、エアーマットほどの快適性や保温性は期待できません。
やはり、防災用として一つはエアーマットを用意しておくことが、災害時のQOL(生活の質)を保つ上で非常に重要だと言えるでしょう。
まとめ:あなたにぴったりのエアーマットで「もしも」に備えよう

この記事では、防災用エアーマットの主要な3つのタイプ(自動膨張式、手動ポンプ・口吹き式、連結・多人数用)を比較し、それぞれの特徴や選び方のポイントを詳しく解説しました。
「エアーマット防災」というキーワードで検索していたあなたが、この記事を読んで、自分にぴったりのエアーマットを見つけるための具体的なヒントを得られたなら幸いです。 災害はいつ、どこで起こるか予測できません。
しかし、備えをしておくことで、その被害を最小限に抑え、心身の負担を軽減することができます。
エアーマットは、避難生活における睡眠の質を大きく左右する重要なアイテムです。 今日からでも、あなたと家族の「もしも」に備えて、最適なエアーマットを選んでみてはいかがでしょうか。
この情報が、あなたの防災準備の一助となり、安心できる未来へとつながることを願っています。
ぜひ、この記事を参考に、一歩踏み出してみてください。

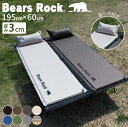




![防災セット SHELTERプレミアム 1人用【楽天総合ランキング1位】 災害対策 おすすめ 非常食 保存食 保存水 ラジオ ライト ランタン エアーマット トイレ ラピタ シェルター 家族 1人分 一人分 一人用 中身 オススメ [AS12]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/at-rescue/cabinet/cat001/pouch/shelter/sh_01_red.jpg?_ex=128x128)
![防災セット SHELTER プレミアム 2人用 【楽天総合ランキング1位】 災害対策 おすすめ 非常食 保存食 保存水 ラジオ ライト ランタン エアーマット トイレ ラピタ シェルター 家族 2人分 ニ人分 ニ人用 中身 オススメ [AS12]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/at-rescue/cabinet/cat001/pouch/shelter/sh_02_tb.jpg?_ex=128x128)


![防災セット SHELTER プレミアム 3人用 【楽天総合ランキング1位】 災害対策 おすすめ 非常食 保存食 保存水 ラジオ ライト ランタン エアーマット トイレ ラピタ シェルター 家族 3人分 三人分 三人用 中身 オススメ [AS12]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/at-rescue/cabinet/cat001/pouch/shelter/sh_03_orbk.jpg?_ex=128x128)


コメント